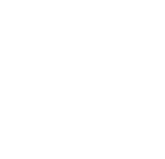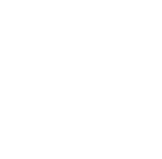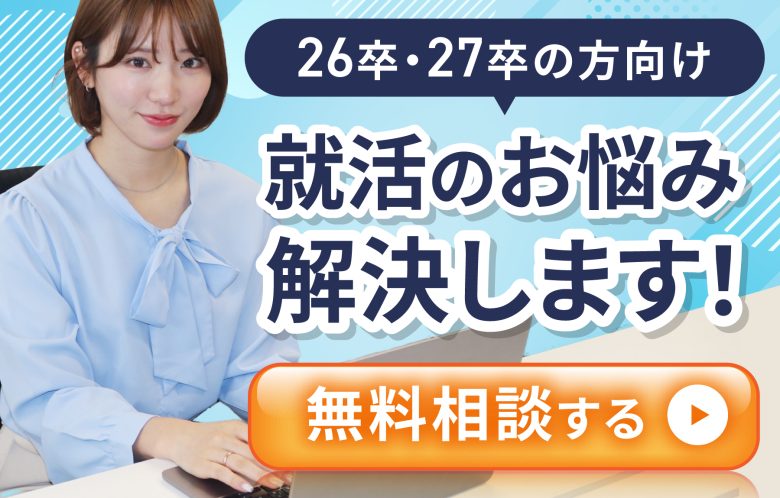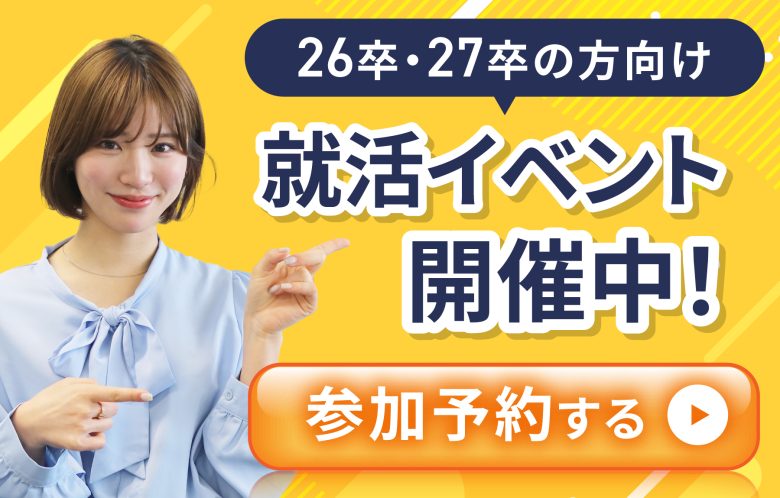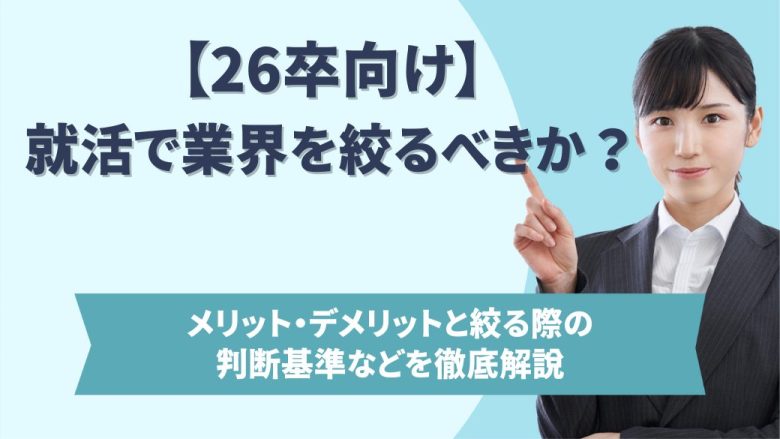
【26卒向け】就活で業界を絞るべきか?メリット・デメリットと絞る際の判断基準などを徹底解説
2025.04.17 更新


監修者
熊谷 直紀
監修者熊谷 直紀
横浜国立大学理工学部卒。株式会社DYMに新卒一期生として2011年に入社し、WEBプロモーションなどのデジタルマーケティング領域で業務に従事し、その後新規事業立ち上げを経験。
2015年よりDYMの人事部へ異動し人事領域を統括、毎年多くの就活生や求職者との面接・面談を実施。
内定チャンネルなどの採用関連メディアへの出演や記事監修を通して人事・人材関連の情報を発信中。
就職活動を始めるにあたり、「志望業界は絞ったほうがよいのだろうか?」と悩む2026年卒業予定の学生(以下、26卒生)は多いのではないでしょうか。
2024年10月に株式会社ワンキャリアが26卒生の大学生を対象にした調査では、26卒生の68.4%が志望業界を2~3業界に絞っているという結果が出ています。
業界を絞っている人がいるのも事実ですが、
「自分に合う業界がわからない」
「業界を絞って内定ゼロになったらどうしよう」
という不安の声もよく聞かれます。
そこで本記事では、就活で業界を絞ることのメリット・デメリットを整理し、絞る際の判断基準などを徹底解説します。さらに、主要な「8大業界」の特徴や、業界以外の観点で企業を絞る方法も紹介します。
自分に合った就活の進め方を見つけ、後悔の少ない就職をしていきましょう。
就活で業界を絞るメリットとは
まず、就職活動において志望業界をある程度絞り込むことで得られるメリットを確認しましょう。
業界を絞ると、効率的に就活を進めるうえでいくつかのメリットがあります。
ここでは主なメリットを3つ紹介します。
- 就活の負担を減らせる
- 特定の業界に集中できる
- 志望動機を整えやすい
就活の負担を減らせる
志望業界を絞る最大のメリットは、就活の負担を減らせることです。
新卒採用を行う企業数は非常に多く、業界を絞らずにそのなかから自分に合う企業を探すのが困難だと感じる人もいるでしょう。
そこで事前に業界を絞っておけば、必然的にエントリーする企業数も絞られ、企業研究やエントリーシート作成、面接対策などにかかる時間・労力を抑えられます。
実際、公益社団法人全国求人情報協会の調査によると、2024年卒業生の就活における平均プレエントリー数は16.8社、書類選考まで受けた会社は平均10.1社となっています。
業界を絞らずに受けようとすると、非常に多数の企業を調べ、そのなかから何社も選別・準備する必要があり、大きな負担となります。
志望業界をある程度絞っておくことで、企業選びを効率化できるのです。
特定の業界に集中できる
業界を絞れば、志望業界の資料集めや研究に集中することができます。
就活においては、1社受けるだけでも準備にかなりの時間を要しますが、業界を絞れば他業界を調べる時間をすべて志望業界の資料集めや研究に充てられます。
その結果、志望業界に関する知識を深められ、選考対策の質を上げることにもつながるでしょう。
たとえばメーカーや商社、IT・通信、マスコミなど、幅広い業界すべてを並行して調べるのは大変です。しかし、志望業界を「IT・通信」と「マスコミ」の2つに絞ったとすれば、それらの業界動向や主要企業について集中的に情報収集できます。
特定業界に的を絞ることで、各企業の特徴や業界内での位置づけ(競合関係、市場シェアなど)も自然と見えてきます。
業界理解が深まれば、志望企業の比較検討や選考での受け答えにも自信が持てるようになるでしょう。
志望動機を整えやすい
志望業界を絞り込んで念入りに業界を調べられれば、説得力のある志望動機作りにも直結します。
1つの業界について深く理解すれば、その業界の事業内容や働き方、各社の社風や待遇の違いまで把握できます。
そうした知見を踏まえて志望動機を書けば、表面的でない踏み込んだ内容となり、採用担当者にも熱意を伝えやすくなるでしょう。
キャリアアドバイザーのなかには、「業界や企業について徹底的に調べて志望動機を作成すれば、より踏み込んだ内容となり説得力が高まる」とアドバイスする方も多くいます。
複数業界にまたがって浅く志望動機を書くより、特定業界に絞って深掘りしたほうが志望理由の質が上がるのです。志望動機は選考の要とも言えるため、説得力のある志望動機を持っていることは、大きな武器・メリットとなるでしょう。
就活で業界を絞るとデメリットはある?
一方で、志望業界を絞りすぎることには注意すべきデメリットも存在します。
メリットだけに目を向けて極端に業界を絞ってしまうと、思わぬ落とし穴にはまる可能性もあるため、事前に把握しておく必要があります。
ここでは業界を絞ることによる主なデメリットを3つ確認します。
- 就活において選択肢を狭めることになる
- 他業界に対する知識が薄くなる
- 一つも内定を得られない可能性が増える
リスクを理解し、対策を講じながらバランスよく業界選びを進めましょう。
就活において選択肢を狭めることになる
志望業界を絞るのは、効率よく就活をするにはよい選択肢ですが、裏を返せば就職先の選択肢を自ら狭めることを意味します。
たとえば、最初から「金融業界しか受けない」と決めてしまえば、それ以外の業界に属する企業は初めから検討リストから外すことになります。
しかし、除外した業界のなかに自分にピッタリ合う企業や魅力的な仕事があったとしても、その可能性に気づけないまま就活を終えてしまうかもしれません。
他業界に対する知識が薄くなる
志望業界を狭く絞り込むと、他業界の知識が浅くなり、視野が狭くなる可能性があります。
特定業界への理解が深まる一方で、「世のなかには他にどのような業界・仕事があるのか」という俯瞰的な視点を失いやすくなってしまうかもしれません。
その結果、自分の志望業界を他業界と比較できず、志望動機が独りよがりで浅くなってしまう恐れもあります。
たとえば面接において「他の業界ではなく、その業界を志望する理由」を問われた際に、他業界を全く見ていないと答えに詰まってしまうかもしれません。
志望業界を絞っていたとしても、他業界にどのような企業がありどう異なるのかは最低限把握しておくことが重要です。そうすることで、志望理由に厚みを持たせられます。
一つも内定を得られない可能性が増える
志望業界を絞りすぎると、最悪の場合「全滅」(一つも内定が得られない)してしまう可能性が増えます。
たとえ志望度が高く熱意があっても、その業界の選考で自分が思うように力を発揮できなかったり、実際には業界自体が自分にマッチしていなかったりすれば、不合格が続いて内定ゼロという事態も当然起こり得ます。
とくに絞った業界が人気で競争倍率が高い場合や、自身の適性と合っていない場合には注意が必要です。
また、業界ごとに募集をかける時期が異なっていることも多いことから、1つに絞って集中的に受けたあと、もしそこが全滅してしまうと、時期によっては他業界でリカバリーする余裕もなくなってしまうかもしれません。
このように、業界を絞ることには視野が狭まり選択肢を失うリスクが伴います。ただし「だから業界を全く絞らないほうがよい」というわけでもありません。
大切なのはメリットとデメリットを理解したうえで、自分に合った適切な範囲で業界を絞り込むことです。
就活では業界を絞るべきなのか
メリット・デメリットを踏まえると、「結局、業界は絞るべきか?」という疑問への答えは、「人それぞれ」となってしまいます。
自分の状況や希望によって、業界を絞ったほうがよい場合と、あえて絞らないほうがよい場合があります。
ここからは、判断のポイントとなる基準を整理し、どのような人が業界を絞ったほうがよいか、逆に絞らなくてもよいかを解説します。
就活で業界を絞ったほうがよい人
以下のようなタイプの就活生は、ある程度業界を絞って就活を進めるのがおすすめです。
- 目指したい業界が明確に定まっている人
- 就活に充てられる時間が少ない人
「昔から憧れている業界がある」「明確にやりたい仕事がある」といったように、具体的なビジョンがある人は業界を絞るのがおすすめです。ただし、同じ業界でも企業ごとに社風や仕事内容はさまざまなので、「企業ごとの差」には目を向けておく必要があります。
次に、学業や研究、部活、課外活動などが忙しい人や、留学などで就活に割ける期間が限られている人は、業界を絞って集中的に準備するのがおすすめです。
広く手を出しすぎると時間が足りず中途半端になりがちなので、自分の興味・適性が高そうな業界に絞り込んで効率よく企業研究や対策を進めるとよいでしょう。
就活で業界を絞らなくてもよい人
一方、以下のような就活生は無理に業界を絞らず、幅広く可能性を探るほうがよい場合があります。
- 目指したい業界が定まっていない人
- 時間的・精神的に余裕がある人
具体的にやりたい仕事や入りたい業界がまだ見つかっていない人は、現時点で無理に業界を一つに絞る必要はありません。むしろ興味のある業界を複数ピックアップしておき、業界ごとの企業をバランスよく受けるような進め方も、ひとつの手段です。
たとえば「ITもメーカーも面白そうで決めきれない」という場合は、その両方で企業研究や説明会参加を行い、自分に合うか探っていくのがおすすめです。最初から一つに決めてしまうとミスマッチに気づけない恐れがあるため、興味の幅があるうちは広めに構えてOKです。
また、就活に十分な時間を割ける人や、色々な業界を見てみたいという探究心が強い人も、最初から業界を絞りすぎないほうがよいでしょう。複数業界に目を向けることで見えてくる共通点や違いもあり、結果的に自身の適性や本当にやりたいことを発見できることもあります。
時間的・精神的余裕がある人はあえて志望業界を狭めず、幅広く企業と出会うきっかけを作るほうがメリットも大きいです。
就活で業界を絞る際のコツ
自分は業界を絞ったほうがよさそうだ」と判断したとしても、絞り方のコツを押さえておかないと、極端に狭めすぎて失敗したり決断が遅れて機会を逃したりする可能性があります。
ここでは、就活で志望業界を絞り込む際に意識したいポイントを3つ紹介します。
- 期限を定める
- ひとつの業界だけにしない
- 事前に自己分析を行う
期限を定める
業界を絞るかどうか迷っている場合でも、「〇月までに志望業界を〇つに絞る」といった期限を自分で定めておくことをおすすめします。ダラダラと決められないまま就活本番に突入すると、準備不足のまま手当たり次第に受けることになりかねません。
実際、内閣府の発表した「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」によると、就活生が企業説明会やセミナー等へ参加した時期(ピーク)は2024年の3月が最も多く、国内企業(ベンチャー企業以外)では6月、国内ベンチャー企業では4月に内々定を出しているところが多いです。
多くの就活生が、早い段階で志望業界を仮決めしておき、行動を開始している傾向にあります。そのため、たとえば「大学4年時の1月までには志望業界を3つに絞っておき、3月前後に開かれる各種イベントに参加し始めるとする」と、いうような計画を立てておくとよいでしょう。
明確な期限を区切ることで、それまでに何をすべきか行動計画も立てやすくなります。
一つの業界だけにしない
業界を絞る際は、「最後まで1業界に絞り切らない」ことも大切です。
志望業界が明確な人でも、基本的には2~3業界程度は候補に残しておくと安心できます。たった一つの業界だけに的を絞ってしまうと、前述したように全滅リスクが高まってしまいますし、業界内で比較対象がなく視野が狭くなりがちです。
たとえば、第一志望の業界に加えて「万が一の場合のセカンド志望業界」を設定しておくと精神的な余裕も生まれます。実際に内定者の声でも、「最初は広告業界だけ狙っていたが、不安になりメーカーも併願した」などと保険的に他業界も受けて結果的にうまくいったというケースは珍しくありません。
初めから進路の可能性を狭めすぎず、メイン+サブの業界を複数用意するのがおすすめです。
事前に自己分析を行う
業界を絞る際の最後のコツは、事前に自己分析をすることです。
自己分析によって仕事に対する自分なりの価値観や評価基準を明確にしておかないと、どの業界に絞るべきか判断しにくくなりますし、仮に絞っても「本当にここでいいのか?」と不安になってしまう可能性があります。
そのため、業界や企業を絞る前に、まず自己分析で自分の強み・弱みや興味の方向性を把握しておきましょう。
自己分析の結果、「人と接するのが好きだからBtoCビジネスの業界にしよう」「安定志向が強いからインフラ業界を軸に見てみよう」といった方向付けをしやすくなります。
逆に「何となく聞こえがよいからこの業界」と決めてしまうと、選考でも志望理由が浅くなり、入社後ミスマッチを感じる恐れもあります。
このように、事前に自己分析を行い、期限を定めていくつかの業界をピックアップすれば、極端な失敗を避けつつメリットを享受しやすくなります。
就活で業界を絞る前に整えておくべきこと
志望業界を絞る前に、土台作りとして取り組んでおくべきことがあります。
それが「自己分析」と「業界ごとの特徴の把握」です。
この二つがしっかりできていれば、どの業界を志望するか検討する際の判断材料が揃い、納得感のある業界選びができるでしょう。
自己分析を行う
繰り返しになりますが、就活のスタートにおいて自己分析は重要です。
自己分析とは、自分の過去の経験や価値観を振り返り、強み・弱みや大切にしたいことを洗い出す作業です。
これにより「自分はどんな仕事に向いていそうか」「何をしているときにやりがいを感じるか」といったヒントが得られます。
たとえば、人と話すのが好きでリーダーシップを発揮した経験が多い人は営業職やサービス業界が向いているかもしれませんし、コツコツ研究するのが得意な人は技術職やメーカーの研究開発職に適性があるかもしれません。
自己分析によって見えてきた方向性をもとに業界を見渡せば、「この業界なら自分の強みを活かせそうだ」「この業界は自分の価値観にフィットしそうだ」といった絞り込みの判断がしやすくなります。
自己分析が不十分だと、仕事に対する自分なりの価値観がないまま何となく人気業界に流されたり、周囲の意見に振り回されてしまいがちです。
まずは自己分析を行うことが、志望業界を選択するために大切な準備と言えるでしょう。
業界ごとの特徴を把握しておく
自己分析と並行して、主要な業界の種類や特徴をざっと把握しておくことも大切です。
業界を知らなければ比較検討のしようがありません。世のなかの仕事は大きく分けるといくつかの業界カテゴリーに分類でき、一般に就職活動では8つの業界に大別されることが多いです。
それぞれの業界が社会で担っている役割やビジネスモデルの違いを理解しておくと、自分がどの業界に魅力を感じるかを絞り込む際の判断材料になります。
たとえば「形ある商品を作り出す仕事がしたい」ならメーカー、「形のないサービスで価値提供したい」ならサービス業界、「社会インフラを支えたい」なら官公庁やインフラ業界、というように結びつけて考えられます。
業界研究の初歩としては、各業界の基本的なビジネス構造(誰に何を提供し収益を上げるか)や代表的な企業・職種などを調べてみましょう。業界地図や就活サイトの解説ページ、本記事の次章で述べる「8つの業界の特徴」などを参考にすると効率的です。事前に広く業界を知っておけば、「こんな業界は今まで興味なかったけど意外と面白そう」と新たな発見につながることもあるかもしれません。
就活で事前に知っておくべき8つの業界の特徴
日本における主要業界は、大きく次の8種類に分類できます。
- メーカー
- 商社
- 小売
- 金融
- サービス・インフラ
- マスコミ
- ソフトウェア・通信
- 官公庁・公社・団体
それぞれの業界の役割やビジネスモデル、代表的な分野について簡単に解説します。業界によってさらに細分化された分野がありますが、ここでは大分類の概要を示します。
志望業界を検討する際の参考にしてください。
メーカー
メーカー(製造業)は、原材料を加工して製品を開発・生産し提供する業界です。
「モノをつくる」現場であり、食べ物や衣服、医薬品など生活に欠かせない品物から、自動車や家電など長期間使用可能な品物、鉄鋼・半導体などの素材や生産設備や機械まで、扱う製品分野によってさまざまな種類のメーカーがあります。
メーカー業界は、製品開発の技術力が競争力の源泉となっていて、景気に左右されやすい面もあります。しかしながら、日本のメーカーは世界的競争力を持つ分野も多いのが特徴です。
商社
商社は、メーカーから仕入れた商品を国内外の取引先に販売し、その差益(仲介料)で収益を得る業界です。
言わばモノの流通を担う中間業者で、扱う分野の広さにより「総合商社」と「専門商社」に分かれます。
グローバルにビジネス展開をしている企業も多く、海外志向の人に人気の業界です。ダイナミックな事業投資やM&Aも手掛けるため、総合職は企画力・語学力など幅広いスキルが求められるのが特徴です。
小売
小売業界とは、メーカーや商社・卸売業者から仕入れた商品を最終消費者に販売する業界です。
私たちが日常的に利用するスーパーやコンビニ、ネット通販などがここに含まれます。最近は実店舗とECを連携させた「オムニチャネル」戦略も注目されています。
消費者と直接接するため顧客志向・サービス精神が非常に重要な業界です。店舗運営や販売職が中心ですが、本部企画やバイヤーなどの職種もあります。近年はデータ分析やIT活用が進み、効率化や新販路開拓(ネットスーパー等)が課題。時代の変遷とともに業態も変化し続ける特徴があります。また、比較的若手でも責任あるポジションを任されやすい業界とも言われています。
金融
金融業界は、お金を動かして利益を得る(お金の流れを仲介する)業界です。
銀行や保険、証券、クレジットカードなどに細分化され、それぞれ扱うサービスは異なりますが、いずれも「資金」を扱う点で共通しています。金融はあらゆる産業と密接に関わり、経済を支える重要な役割を持ちます。
経済やマーケットの知識が不可欠で、景気や政策の影響を受けやすい業界です。安定したイメージがある一方、フィンテックなど技術革新で変化が大きい分野でもあるのが特徴です。
サービス・インフラ
サービス・インフラ業界は、形のないサービスを提供することで対価を得る業界です。
範囲が広く、不動産から交通、物流、電力、ガスなどのインフラ系、旅行やホテル、飲食、などの人材サービス、教育や医療、福祉、コンサルティングまでさまざまな業種が含まれます。
顧客が求めるサービスを時代に合わせて創出することが重要で、サービス業全般でイノベーションが盛んな業界です。景気や社会の変化に伴い新サービスも次々登場します。人との関わりが多い業種が多く、ホスピタリティ精神や提案力が求められる場面が多いのが特徴です。
マスコミ
マスコミ(マスコミュニケーション)業界は、情報を多くの人に一度に伝達し、その対価で利益を得る業界です。
具体的には、テレビやラジオなどの放送、新聞などの出版・新聞、広告代理店などの広告が代表的です。近年はインターネットメディアも台頭していますが、ここでは伝統的マスメディア中心に説明します。
放送局や新聞は視聴者・読者数を集めて広告料収入を得るモデルが中心。広告代理店は企業から広告予算を預かりメディアに広告枠を買って掲載する仲介。出版社はコンテンツ販売や広告で収益。このように、業界のなかでも業種により収益モデルが異なります。
また、社会への影響力が大きい反面、近年はネットの普及でビジネスモデルの転換期を迎えている業界です。総じて人気業界で競争倍率が高いと言われますが、激務な現場も多い特徴もあります。「情報発信で世のなかを動かしたい」という熱意ある人には魅力的でしょう。
ソフトウェア・通信
ソフトウェア・通信業界は、情報の伝達や処理・加工に関わるサービスを提供する業界です。
いわゆるIT業界であり、企業向けのシステム開発を行うソフトウェア(ITサービス)企業、インターネット上でコンテンツやサービスを提供する企業、通信インフラ(携帯通信など)を提供する通信事業者などが含まれます。
常に技術革新が起きるため変化が激しく、ベンチャー企業も多い業界です。今後も市場成長が見込まれ、デジタルトランスフォーメーションの担い手として注目されています。理系だけでなく文系出身者も多く活躍しており、ポテンシャル採用が比較的盛んなのも特徴です。
官公庁・公社・団体
官公庁・公社・団体は、国や地方自治体の行政機関、および公的な事業を行う団体です。
民間企業ではないため厳密には「業界」と異なりますが、新卒の就職先として一定数の学生が志望する領域です。国家公務員や地方公務員、独立行政法人、各種公益法人、学校・病院などが該当します。
安定性が高く公共性が強い仕事が多く、営利追求ではなく社会貢献や国民生活の向上を使命としているところも多い業界です。給与は税収や予算に左右され、民間のような大幅昇給は少ない反面、雇用は安定している傾向があります。公務員試験など独自の採用ルートになるため、他業界とは異なる準備をする必要があるのが特徴です。
就活で業界を絞る際の7つの考え方
志望業界を絞り込む際には、自分なりの考え方を持って分析することが大切です。
ここでは、業界選択を進めるうえで参考になる7つの考え方を紹介します。迷ったときはこれらのポイントに立ち返って検討してみましょう。
- 自己分析の結果と照らし合わせる
- 理想とするキャリアビジョンを考える
- 避けたいことや譲れないことをまとめる
- 希望する条件を一覧化する
- 興味のある企業をまとめる
- Will・Can・Mustのフレームワークで考える
- 第3者からアドバイスをもらう
1.自己分析の結果と照らし合わせる
まず第一に、自己分析の結果を軸に業界を検討することです。
自己分析で明らかになった「自分が重視したい価値観」「自分の強み・弱み」「自分が興味のある分野」「自分が嫌だと感じること」などを書き出し、それに合致する業界はどこか、逆にミスマッチな業界はどこかを考えます。
よく「就活の軸」という言葉が使われていますが、就活においてとくに軸となるのは「自分が重視したい価値観」や「自分の強み・弱み」です。
たとえば「安定志向で地元志向が強い」のであれば地方銀行やインフラ業界が候補に挙がるでしょうし、「海外で働きたい」「チャレンジ精神旺盛」なら商社やコンサル業界が向いているかもしれません。
自己分析で出てきたキーワードを業界の特徴とマッチングさせるイメージを持ち、軸がぶれなければ、たとえ周囲が人気業界に流れていても自分の判断を貫けるはずです。
2.理想とするキャリアビジョンを考える
すでに理想とするキャリアビジョン(なりたい社会人像)があるのであれば、将来のキャリアビジョンから逆算して業界を考えるのも有効です。
就職はゴールではなくキャリアのスタートです。10年後、20年後に自分がどうなっていたいか、そのためにどのような経験を積みたいかを思い描いてみましょう。
たとえば「将来は経営者になりたい」というビジョンがあるなら、若いうちから経営視点を養える環境である「ベンチャー企業」や「コンサル業界」などが向いているかもしれません。「専門性を極めたい」なら「メーカー業界」で技術職に就くとか、「世界を舞台に活躍したい」なら商社や海外展開の盛んな業界、といった具合です。
もちろん最初から明確な将来像を持つのは難しいです。まずは「〇〇のスキルを身につけたい」「△△な働き方がしたい」といった希望でも構いません。
自分の夢や希望を実現できそうな業界をリストアップしてみましょう。キャリアビジョンという視点で業界を見ることで、「憧れ」だけでなく将来性も含めた判断ができます。
3.避けたいことや譲れないことをまとめる
業界を選ぶ際には、「自分が絶対に避けたいこと」「ここだけは譲れない条件」をはっきりさせておくのも重要です。
これは裏を返せば、業界を消去法で選ぶ方法でもあります。
たとえば、「転勤したくない」「土日休みが欲しい」「成果主義すぎる社風は嫌だ」などの条件があれば、それに当てはまらない業界・企業を除外できます。
具体例を挙げるとすれば、「勤務地を地元限定にしたい」なら全国転勤が多い総合商社や大手メーカーは避けて地域密着の地銀や地方公務員を選ぶ、といった判断ができます。「ノルマ営業は絶対無理」という人は、個人向けの保険営業や不動産販売を避け、反対にノルマのない企画職の多い業界を検討するとよいでしょう。
自分にとって譲れない条件を3つ程度書き出し、それに反する業界は候補から外して構いません。すべてを満たす業界は難しくても、絶対嫌なことを避けるだけでも後悔の少ない選択につなげられます。
4.希望する条件を一覧化する
避けたい業界や業種の条件をまとめる方法をすでに紹介していますが、ポジティブな視点で「希望する就職先の条件」をリストアップしておくのも重要です。
「勤務地、給与水準、福利厚生、働き方、企業規模、社会貢献度、将来性など…」人によって重視するポイントはさまざまです。それらに優先順位をつけて、より多く満たす業界はどこかを考えます。
たとえば「年収はできるだけ高いほうがいい」という希望が強ければ、平均年収の高い金融や総合商社、コンサルなどが候補になります。「ワークライフバランス重視」なら、残業が比較的少ない傾向にあるインフラ系や公務員が向くかもしれません。「勤務地は首都圏限定」なら、地域限定採用のある企業や東京本社の多い業界がターゲットになるでしょう。
このように自分の希望条件と業界特性を突き合わせ、合致度の高い業界を探すことで、納得感のある絞り込みができます。ただし完璧に条件を満たす業界・企業は少ないため、何を優先し何を妥協するかの取捨選択も必要です。
5.興味のある企業をまとめる
業界から考えるだけでなく、興味のある企業リストを作ってみるのもよいアプローチです。
具体的に企業名を思い浮かべられる企業はいわば「自分が気になる会社」とも言えます。その企業が属する業界は候補に入れやすいです。10社でも20社でもよいので、まずは気になる企業を書き出してみましょう。
たとえばリストにトヨタ、ソニー、資生堂とあれば製造業(メーカー)が好きなのかもしれませんし、三菱商事、伊藤忠が入っていれば商社に憧れているのかもしれません。Google、楽天、NTTデータが入っていたらIT業界志望と言えそうですし、日本銀行、経産省などがあれば公共セクターに興味があるのでしょう。
このように、自分のアンテナに引っかかった企業の業界を分類してみると、自分の志向が見えてくることがあります。「あまり意識していなかったけど自分は〇〇業界の企業ばかりに興味を持っていたんだな」と気づけば、その業界を重点的に研究してみる価値があるでしょう。
6.Will・Can・Mustのフレームワークで考える
自己分析の手法として有名な「Will・Can・Must」のフレームワークを業界選びに活用してみるのもおすすめです。
Will(やりたいこと)、Can(できること)、Must(やるべきこと)の3軸からキャリアを考える方法で、自分の価値観や強みに沿ったキャリア設計ができ、入社後のミスマッチ防止にもつながると言われます。
| Will(意志・やりたいこと) | 自分が情熱を持ってやりたいと感じる仕事や使命は何か |
| Can(能力・できること) | 自分が得意とするスキルや強みは何か |
| Must(責任・やるべきこと) | 社会や周囲から期待されている役割、果たすべき責任は何か |
この3つが重なる領域に、自分が力を発揮できるキャリアがあると言われます。業界選びにおいても、Will(やりたい仕事)が存在し、Can(自分の強み)を活かせることができ、Must(社会的意義)も感じられる業界はどこかを考えてみましょう。
たとえば「人の暮らしを支えたい(Will)」「理系で工学の知識がある(Can)」「社会インフラを維持する(Must)」という人ならインフラ業界がそれに当たるかもしれません。
自分の「Will・Can・Must」を明確にしておけば、志望動機にも説得力が増します。自分の内面と社会的役割の接点として業界を捉えることで、長期的に見て後悔のない選択ができるでしょう。
7.第3者からアドバイスをもらう
自分一人で考えていて行き詰まったら、信頼できる第3者に相談するのも有効です。
大学のキャリアセンターの相談員、就活エージェントのキャリアアドバイザー、OB/OG、ゼミの先輩や社会人の知り合いなど、客観的な視点をくれる人に話を聞いてもらいましょう。ときには、自分では思いもよらなかった業界の可能性を指摘してくれるかもしれません。
たとえばキャリアアドバイザーとの面談で「あなたの強みなら〇〇業界の△△職種で活かせそうですね」とアドバイスされ、「その業界は考えていなかったけど興味が湧いてきた」というケースも多いようです。
また、家族や友人など自分をよく知る人から率直な意見をもらうのもよいでしょう。「あなた〇〇が得意なんだから△△業界とか向いてるんじゃない?」という何気ない一言がヒントになることもあります。第三者の視点は新たな気づきをもたらすので、ぜひ積極的に活用してください。
就活で業界を絞るのに参考にできる行動
業界を絞り込む際には、机上で考えるだけでなく実際の行動を通じて業界研究を深めることが大切です。
ここでは、志望業界を決めるヒントを得るために有効な具体的な次の行動例を紹介します。
- 会社説明会や合同説明会に参加する
- 就活エージェントを活用する
- インターンシップに参加する
- OB訪問を活用する
積極的に動いて情報を集め、自分の肌感覚で業界の雰囲気や適性を確かめましょう。
会社説明会や合同説明会に参加する
志望業界を深く探るには、企業の説明会に参加して生の情報を聞くのが非常におすすめです。
特定企業の単独会社説明会も有益ですが、とくに就活初期で業界比較をしたい段階では合同企業説明会(合説)を活用しましょう。
合同説明会なら一度に複数社が集まり、短時間で多くの企業の話を聞けます。さまざまな業界から企業が出展しているイベントに行けば、幅広い業界を知り、比較することも可能です。
たとえば、「興味がなかったけれど合説で話を聞いたら意外と面白そうだった」という発見が生まれることもあります。実際、合同説明会に参加すると「こんな業界があったのか」「自分に合いそうな優良企業を見つけた」という学生も多いです。
ただし全く予備知識がないと得るものが少なく終わってしまうので、参加前に簡単に業界情報をチェックしておきましょう。
そして当日は積極的に質問し、各企業の担当者の話しぶりや雰囲気から業界の空気感を感じ取ってください。説明会での出会いは業界を絞る大きなヒントになります。
株式会社DYMが運営する就活サポート「Meets Company」では、就活生が安心して就活サポートを受けられる信頼性の高いサービスの提供や、企業の社長や人事と直接話すことができる合同説明会の開催を行っています。
就活生は「Meets Company」が提供するサービスを無料で受けられるのが特徴です。就活のプロから業界選びのアドバイスを受けられるだけでなく、合同説明会に参加してグループワークを通じ、実践的な就活経験を積み上げることも可能。さらに、合同説明会の最中に書類選考から面談へつなげられることがあるだけでなく、リアルタイムで人事担当者からフィードバックを受けられるため、自分を成長させる大きな機会にもなるでしょう。
「Meets Company」を最大限に活用してみてはいかがでしょうか。
就活エージェントを活用する
就活エージェントサービスを利用して、プロのアドバイザーに相談するのも有効です。
知識や経験豊富なエージェントが、あなたの適性や希望をヒアリングしたうえで業界・企業選びのアドバイスや推薦をしてくれます。
自分では視野に入れていなかった企業を紹介してもらえることもあり、「こんな業界・会社もあったのか」と知るきっかけになります。また、エージェント経由で応募すれば選考対策のフォローも受けられるため、効率よく複数業界を受けることができます。
たとえば、IT業界に強いエージェント、人材業界に強いエージェントなど、それぞれ得意分野があるので、自分の志望に合いそうなエージェントを選ぶとよいでしょう。
「業界研究のアドバイス」「適性診断」「企業紹介」といったサービスを無料で提供しているところがほとんどです。
エージェントは企業側の求人事情にも詳しいため、人気企業以外にも隠れた優良企業を教えてくれることがあります。「自分に合った業界・企業がわからない」という人は、ぜひエージェントに相談し、客観的な視点を取り入れてみましょう。
エージェントサービスを提供している企業が多く、どれを選べばよいか判断がつかない人は、エージェントサービスも合同説明会も提供している「Meets Company」を活用してみてはいかがでしょうか。
インターンシップに参加する
インターンシップは、業界・企業を肌で感じられる絶好の機会です。
とくに夏や秋に開催される就業体験型インターンに参加すれば、その業界の仕事の一端を実際に体験可能です。参加学生のアンケートでも、インターン参加の目的として「企業理解を深めるため」と答える人が56.2%、「業界理解を深めるため」と答える人が49.2%に上ったという結果が出ており、企業・業界理解を深めるための有効な手段です。
インターンに参加すると、「この業界の仕事は自分に合いそうだ」「思っていたイメージと違うな」と業界との相性を確かめられます。
たとえば、銀行のインターンで金融業界の雰囲気を知り志望を固めた人もいれば、逆にメーカーのインターンで工場の現場を見て「ものづくりは向いていないかも」と気づく人もいるかもしれません。参加前と後で志望業界が変わることは珍しくありません。
また、インターンを経験すると本選考でも具体的な志望動機を持っていると判断されることがあります。たとえ志望業界から外れても、経験として無駄になることはありません。
ぜひ興味のある業界のインターンには積極的に応募し、自分の目で業界を体感して判断材料を得ましょう。
OB訪問を活用する
大学のOB・OG訪問も業界研究に大いに役立ちます。
実際にその業界で働く先輩社員のお話を直接伺えるため、ネットや本には載っていないリアルな情報が得られます。ある調査では、OB訪問のメリットとして55.6%の学生が「やりたいと思っていた仕事のイメージがはっきりしたこと」を挙げています。
OB訪問では、「その業界を選んだ理由」「仕事のやりがい・大変さ」「他業界と迷わなかったか」など、先輩自身の経験に基づく話を聞いてみましょう。
たとえば、広告業界の先輩から「華やかなイメージだったけど実際は地道な作業も多い」など率直な声を聞ければ、自分の覚悟も定まります。また、「他の業界も見たけどやっぱり今の業界が合っていた」という話で安心することもあるでしょう。
就活経験者の生の声は非常に説得力があります。OB訪問を通じて得られた気づきは、業界選びのみならず、その後の面接でのエピソードトークにも活きるはずです。
大学の先輩だけでなく、社会人とのマッチングサービスなどもうまく使って、興味のある業界のほうに積極的に話を聞いてみてください。
就活で業界を絞るときに注意すべきこと
最後に、業界を絞る際に陥りがちな注意点・NGパターンを押さえておきましょう。
これらに気をつければ、絞り込みの失敗リスクを減らし、柔軟で後悔のない就活ができるはずです。
- イメージだけで業界を絞ること
- 好きという感情だけで業界を絞ること
- 早い段階から業界を絞ること
- 一度絞った業界にこだわりすぎること
イメージだけで業界を絞ること
漠然としたイメージだけで業界を決めつけるのは避けましょう。
たとえば、「IT業界=なんだかキツそう」「金融=堅苦しそう」「メーカー=安定」など、世間一般のイメージだけで合う・合わないを判断してしまうのは危険です。実際に働いてみるとイメージと違った、というギャップはどの業界でも起こり得ます。
とくに「華やかに見えるからマスコミ志望」「オシャレそうだからアパレル志望」といった理由で絞るのは要注意です。その業界の裏側(長時間労働や競争の厳しさなど)も含めて理解したうえで判断しないと、入社後「こんなはずじゃなかった」となりかねません。
業界イメージだけにとらわれず、中身をきちんと調べるようにしましょう。
好きという感情だけで業界を絞ること
志望業界を選ぶ動機として「その業界が好き」「興味がある」というのは大切ですが、「好き」だけで突っ走りすぎないことも重要です。
たとえば、「ゲームが好きだからゲーム業界!」と決め打ちするのは一見わかりやすいですが、ファン目線と仕事として携わるのは別物です。好きすぎるあまり冷静さを欠き、「単なるファン」にとどまってしまうと志望理由も浅くなってしまいます。
実際、「その業界が大好き」という思いが強い人ほど、面接でファン的な話になってしまいがちです。仮に好きという感情を原動力としたいのであれば、「好きだからこそ業界をこう変えたい」「この課題を解決したい」という視点まで踏み込む必要があります。ただ好きなだけではなく、仕事として向き合える覚悟と具体的な動機を持てるか自問してみましょう。
好きな業界でも、自分が活躍できる職種があるか、働き方は受け入れられるかなど冷静に見極めることが大切です。
早い段階から業界を絞ること
就活解禁前の早い時期から志望業界を一本化してしまうのも、リスクがあります。
明確な志望動機や目標がある人はよいのですが、大学3年の夏以前から業界を固定して動くと、後から「他の業界も見ておけばよかった」と後悔するケースがあります。
実際、10月時点で志望業界を2~3に絞っている学生が多数いる一方で、その後志望業界を広げる可能性にも言及されています。業界の志望は3年1月頃から固まりだすのが一般的との見解もあります。
夏秋に多いインターンや企業研究を経て、自分の志望が変化することもあるでしょう。仮に志望業界を決めて動き出しても、途中で「やっぱり違う」と思ったら勇気を持って方向転換して構いません。焦って早期に縛りすぎると選択肢を自ら減らすことになるので注意しましょう。
一度絞った業界にこだわりすぎること
志望業界を一度決めたからといって、最後まで意地になってその業界だけに固執しないことも大事です。
就活を進めるなかで「なんとなくこの方向ではない気がする」と感じたり、選考が思うように進まず不安になったりすることもあるでしょう。その場合、頑なにこだわり続けるより視野を広げることが打開策になる場合があります。
実際、「食品業界しか受けない」「マスコミ以外は考えない」とこだわりすぎて他が目に入らなくなっているケースはよくあります。しかし内定が得られなかったり、途中で興味が変わったりした場合には、「方向転換はあり」です。
一度絞ったからといって自分を縛りすぎず、柔軟に志望業界を見直す心構えも持っておきましょう。こだわりすぎは禁物ですが、逆にぶれすぎるのもよくないので、軸が揺らいできたら再度自己分析に立ち返ることが重要です。
就活で業界を絞ったあとに変更したいと感じたら?
就活を進めるなかで、「やはり志望業界を変えたい」「他に興味の持てる業界が出てきた」と感じることは珍しくありません。その場合は早めに行動すれば十分軌道修正は可能です。
具体的には以下のようなステップで対応しましょう。
- 志望業界を変えたい理由を整理する
- 新たに興味の湧いた業界について情報収集する
- 周囲やキャリアセンターに相談する
- 志望業界変更後のスケジュールを立て直す
まずは何が違和感の原因か、なぜ方向転換したいのかを明確にします。「選考で落ち続けて自信をなくしたから」なのか「本当に興味が移った」のかを自己分析しましょう。
次に、変更を考えている業界のことを改めて調べましょう。業界研究やOB訪問を集中的に行い、本当に志望するに値するか確認します。他業界を見ることでもとの志望業界の良さを再認識する場合もあります。
不安であれば、大学のキャリア相談や信頼できる先輩に相談してみましょう。第三者の意見を聞くことで自分の気持ちが整理されます。
変更する業界が定まったら、新たに受ける企業の募集時期や選考スケジュールを確認し、間に合うように準備します。エントリー締切やインターン参加など、今からできることをリストアップしましょう。
仮に就活後半になってから業界を変える場合でも、諦める必要はありません。自身で必要と感じたら、勇気を持って舵を切り直しましょう。その経験自体がきっと糧になるはずです。
ただし、変更理由については、面接などで「なぜ途中で志望業界を変えたのか?」と問われる可能性があります。その際に一貫性がないと思われないよう、前向きな動機と納得感のあるストーリーを用意しておくことが大切です。自己分析の深化や新たな発見があったことを伝えられれば問題ありません。
就活で業界以外に企業を絞る方法
ここまで業界という軸での絞り方を見てきましたが、企業を選ぶ基準は業界以外にもさまざまな切り口があります。
最後に、業界にとらわれず企業を絞り込む方法の例を紹介します。「どうしても業界が決められない」という人は、次の観点から企業選びを進めるのも一つの戦略です。
- 志望条件や待遇で絞る
- 職種で絞る
- 企業が勧める魅力で絞る
- 就活エージェントなどを活用してアドバイスをもらう
志望条件や待遇で絞る
自分が重視する志望条件(勤務地、給与、福利厚生、安定性など)や待遇面から企業を絞り込む方法です。
たとえば「年収〇〇万円以上出してくれる会社」「完全週休二日制で定時退社ができる会社」などの条件を設定し、それを満たす企業を業界問わず探します。最近は多くの就活サイトで「年間休日120日以上」「リモートワーク可」など条件検索が可能です。
また、「従業員数〇〇人以上の大企業」「上場企業」「ベンチャー」など企業規模で絞るのも手段の一つです。たとえば「安定重視だから社員1万人規模の大手企業」を軸にすれば、インフラ・メーカー・金融など大企業の多い業界がターゲットになるでしょう。逆に「少数精鋭の環境がいい」ならベンチャーや中小企業を狙い、そうした企業の情報を集めます。
この方法では業界という分け方に注視していないため、結果的に複数業界にまたがった企業群が志望先に並ぶこともあります。それでも、自分の希望条件を満たす企業であれば志望動機も作りやすいでしょう。
ただし「条件ありき」だと面接で伝えにくい場合もあるため、企業ごとの魅力もしっかり調べておくのが大切です。
職種で絞る
職種(やりたい仕事内容)で企業を絞るのも有効です。
「営業職でバリバリ働きたい」「企画職志望」「研究開発職志望」など、やりたい職種が明確なら、その職種採用のある企業を業界横断で探せます。
たとえば「商品企画がやりたい」ならメーカーや食品会社、アパレルなどさまざまな業界で商品企画職の募集がありますし、「コンサルティングがしたい」ならコンサル業界以外にもIT企業のコンサル部門などがあります。
また「〇〇エンジニアになりたい」という技術職志望なら、IT・メーカー問わずそのスキルを活かせる企業を探せます。職種軸で考えると、業界の枠を超えて自分のやりたい仕事にフォーカスできるのがメリットです。
注意点としては、企業によって同じ職種名でも役割が違ったり、総合職採用だと職種を選べなかったりするので、募集要項をよく確認しておくようにしましょう。
職種志望の場合は、「なぜその職種か?」が志望動機の肝になります。業界に縛られない分、職種への熱意や適性を説得力を持って語る準備が必要です。
企業が勧める魅力で絞る
各企業は採用サイトや説明会で自社のアピールポイント(魅力)を打ち出しています。「若手にも裁量権」「グローバルに活躍」「研修充実」「社会貢献性」などさまざまです。こうした企業の推しポイントに共感できるかどうかで絞る方法もあります。
たとえば「社員の仲がよいアットホームさをアピール」している企業に魅力を感じるなら、そうした社風を持つ企業を選ぶ、逆に「成果主義で切磋琢磨」に惹かれるならそうした文化の企業を選ぶ、といった具合です。
業界が違っても、「人を大事にしている会社がいい」「技術力を追求している会社がいい」など自分の価値観にフィットする企業を選び抜けば、結果的に志望企業群が見えてきます。
具体的には、企業研究を通じて企業ごとの特徴を比較表にするのがおすすめです。自分が魅力に思うポイントを〇△×などで評価し、合致度の高い企業を残していきます。業界関係なく「この会社で働きたい」と思える企業が見つかれば、その熱意は面接でも伝わります。
就活エージェントなどを活用してアドバイスをもらう
前述した就活エージェントを再度活用したり、大学のキャリア支援に相談したりして、自分に合う企業をプロに紹介・推薦してもらうのもひとつの手です。
業界にこだわらず「自分の強みや志向にマッチした企業」を提案してもらえば、新たな発見があります。
たとえば、自己分析の結果を伝えたうえで「自分に合う会社ってどのようなところでしょう?」と聞いてみると、第三者視点で思いもよらない企業名が出てくるかもしれません。「このタイプの人は意外と〇〇業界で活躍していますよ」など有益な示唆を得られるかもしれません。
自分で企業選びの軸を決めきれない場合は、遠慮なくプロの力を借りましょう。最終的に決めるのは自分ですが、専門家の知見は非常に心強い味方です。とくにエージェント経由で応募すると書類選考免除などのメリットもあるため、効率よく企業を絞り込みたい場合にもおすすめです。
まとめ
就活で業界を絞るべきかどうかは、一概に「絞った方がよい」「絞らない方がよい」どちらとも言えない問題です。大切なのは、自分の状況や価値観に照らして最適なアプローチを選ぶことにあります。
業界を絞るメリットには、「就活の負担軽減」や「業界研究に集中できる」などがあります。一方で、自ら就活における選択肢を狭めてしまうデメリットがあるのも事実です。
まずは、自分は本当に業界を絞るべき人か否かを判断し、仮に絞る場合も期限を設けたり1業界に固執しないといったコツを実践しながら就活に臨みましょう。
どうしても自分だけでは判断しきれないのであれば、ぜひ無料でアドバイスを受けられる「Meets Companyの就活サポート面談」を活用してみてください。
あなたにとって最良の選択肢が見つかるよう、本記事の内容がヒントになれば幸いです。悔いの残らない就活になるよう、応援しています!