

Webテスト「玉手箱」対策まとめ|SPIとの違いや問題例を紹介

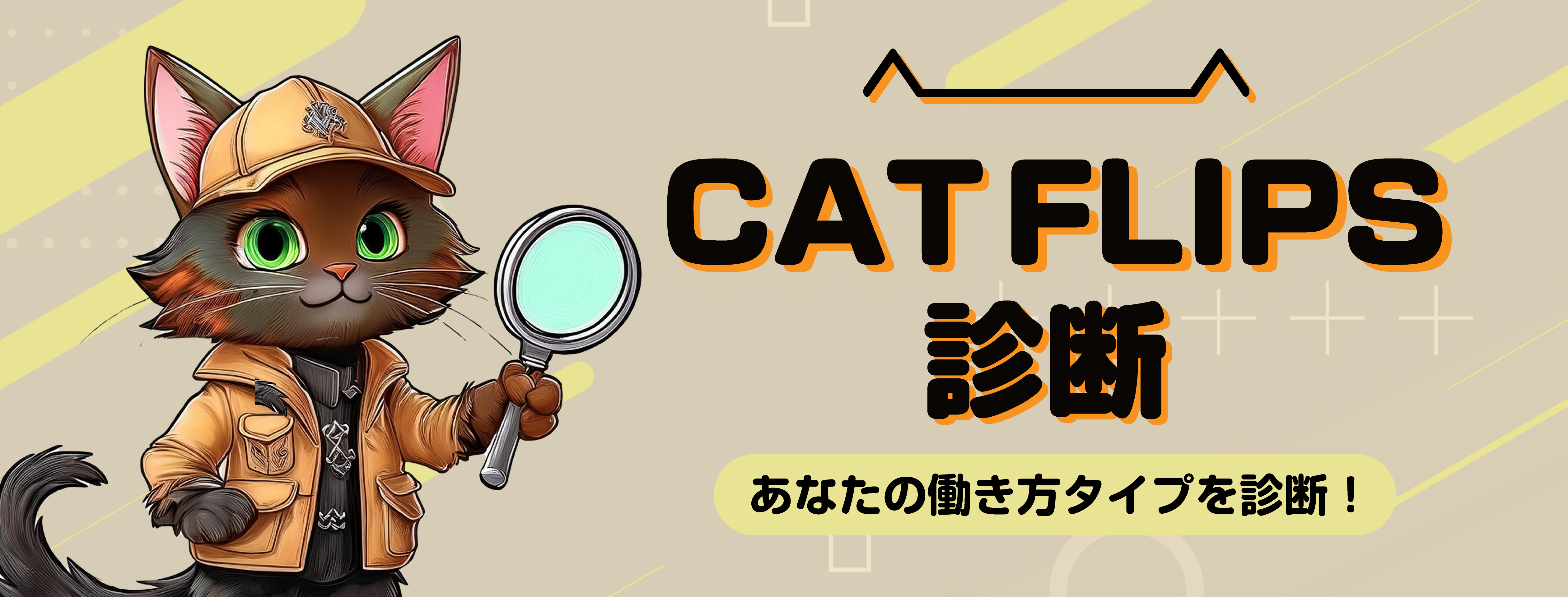
新卒の就活で多くの企業が導入している「玉手箱」について対策の仕方を解説します。
就活生から敬遠されがちなWebテストの対策。
Webテストは、その法則やコツを掴むとかなり解きやすくなります。
玉手箱で高得点を狙うには、事前の対策が不可欠です。
効率的に対策ができるよう、ポイントを掴んでいきましょう。
目次
Webテスト「玉手箱」とは?

玉手箱とは、就活生に人気の大手企業や有名企業が多数導入しているWebテストです。
数あるWebテストのなかでも「自宅受験型」のなかでトップシェアを誇っています。
Webテストには、自宅のパソコンで受験をする「自宅受験型」と、テストセンターへ足を運び専用のパソコンで受ける「テストセンター型」があります。
野村證券、日立製作所、日本生命保険、東京ガス、JR西日本などの人気企業が玉手箱を新卒採用で導入しています。
玉手箱には独自の出題傾向や特徴が存在するので、それらを押さえて効果的な対策ができるようにしましょう。
Webテスト「SPI」との違い
SPIはリクルートマネジメントソリューションズが実施している適性検査です。
玉手箱とSPIの最大の違いは、玉手箱はテストに時間制限があるのに対し、SPIは問題ごとに時間制限がかけられています。
また、SPIでは一度の試験内でさまざまなジャンルからの出題があるのに対し、玉手箱では同じジャンルの問題のみが連続して出題されます。
出題方式やテスト形式が異なるため、就活を進めるためには両方の対策が必要になります。
Webテスト「玉手箱」の出題科目

玉手箱で出題される科目は「計数問題」「言語問題」「英語問題」です。
それぞれの科目の特徴を解説します。
【対策】計数問題の出題形式
計数問題は主に「数学」の問題で、「四則演算」「図表の読み取り」「表の空欄推測」のジャンルから出題されます。
「四則逆算」は、四則の計算式の一部分が空欄になっており、当てはまる数字を回答する問題です。
50問の問題を9分間で解かなければならないため、計算を素早く正確におこなう能力が必要になります。
「図表の読み取り」は棒グラフや円グラフなどから数字を読み取り、計算をする問題です。
素早い計算のほか、グラフを読み取る力が必要になります。
「表の空欄の推測」は表に記されている数字から法則を導き出し、空欄に入る数字を特定するものです。
表を見てすぐに概算や規則性を見出す必要があり、瞬発力が求められる問題です。
【対策】言語問題の出題形式
玉手箱における言語問題は「国語」の科目から出題され、「論理的読解」「趣旨判定」「趣旨把握」に分けることができます。
「論理的読解」は、文章の内容と設問に書かれている内容が一致しているかどうかを判断する問題です。
「趣旨判定」は、文章と、問題に書かれている短文の関係性を選択するものです。
「趣旨把握」は、文章が結論として何を言いたいのかを読み取る問題です。
共通して単語の知識や思考力が必要となるほか、長文を難問も読まなければならないため、素早く要点を読み取る力も重要になります。
【対策】英語問題の出題形式
英語の問題は「論理的読解」「長文読解」の2つのジャンルに分けられます。
「論理的読解」は文章を読み設問に書いてある内容が正しいかどうかを回答する問題です。
基礎的な英語力が試され、単語力や文法力が試されます。
「長文読解」は、その名のとおり長めの文章を読み、設問に答える問題になります。
長文読解は、基本的な単語を知っているだけでなく、いかに英語を読むことに慣れているかということがポイントです。
就活で頻出!Webテスト「玉手箱」の特徴
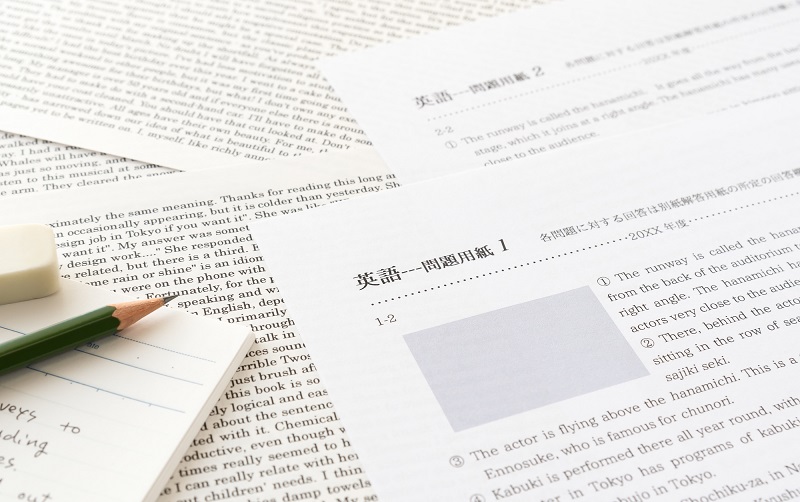
玉手箱で出題される問題が持つ特徴を確認していきましょう。
どのような出題形式なのか、ほかのWebテストとは何が違うのかということを知り、理解を深めていってください。
問題の順番はランダムに出題されるが、出題ジャンルは一種類のみ
玉手箱の問題は、1番はこの問題、2番はこの問題というように問題が固定されておらず、何番にどんな問題が来るかはランダムで決まります。
同じ問題を出したり、同じ順番になったりすることのないような仕組みを導入しているためです。
出題されるジャンルは同一のものから出題されます。
たとえば、計数問題で「四則演算」と「図表の読み取り」の両方から出題されることはありません。
問題を解く時間が短い
玉手箱の特徴として「制限時間が厳しい」ことが挙げられます。
問題数や読む文章の量に対して設けられている時間が短く、ひとつの問題で使える時間が限られてきます。
計算問題が得意でも、このテンポに慣れていないとすぐに置いていかれてしまいます。
たとえば計数問題のなかの「四則逆算」では50問を9分間で解かなければならないため、1問あたりにかけることのできる時間は10秒程度ということになります。
それぞれの問題の難易度は高くない
玉手箱の各問題の難易度はそこまで高くありません。
玉手箱を受けるにあたっては「比較的簡単な問題を、短時間で多くさばく」ことが求められています。
対策としては、複雑な問題をじっくり考えるタイプのWebテストとは違い、テンポよく問題を解いていく練習をしておくと効果的です。
就活で玉手箱は対策必須!その方法

玉手箱の対策をするときのコツをお伝えします。
玉手箱の問題を賢くこなしていくためにはいずれも欠かせないポイントです。
ぜひ参考にして対策を進めてください。
【対策1】問題形式を覚える
玉手箱では、事前に問題のパターンを覚えておくことが非常に重要になります。
問題のパターンを把握しておけば、どんな問題もパターンに当てはめて解くことができるからです。
玉手箱はどんな形式の問題が出るかということがあらかじめ分かっています。
効率的に問題を解く練習をしていきましょう。
【対策2】わからない問題は飛ばす
玉手箱を解くときはわからない問題で足を止めることはせず、無視をしてしまいましょう。
制限時間に対し問題数が非常に多い玉手箱では非常に有効になる進め方です。
わからない問題を解くよりも、わかる可能性のある次の問題に取り掛かることを優先しましょう。
一問にかける時間を事前に設定しておくと効果的です。
【対策3】電卓を使う練習をしておく
玉手箱の計算問題は秒単位での勝負になるため、電卓を使いこなせると有利になります。
計数問題ではかなりの計算スピードが必要になります。
大きな数を使う計算が多いため、必ず電卓を使う練習をしておきましょう。
電卓は使えば使うほどスムーズに使いこなせるようになります。
【問題例あり】玉手箱の科目別例題
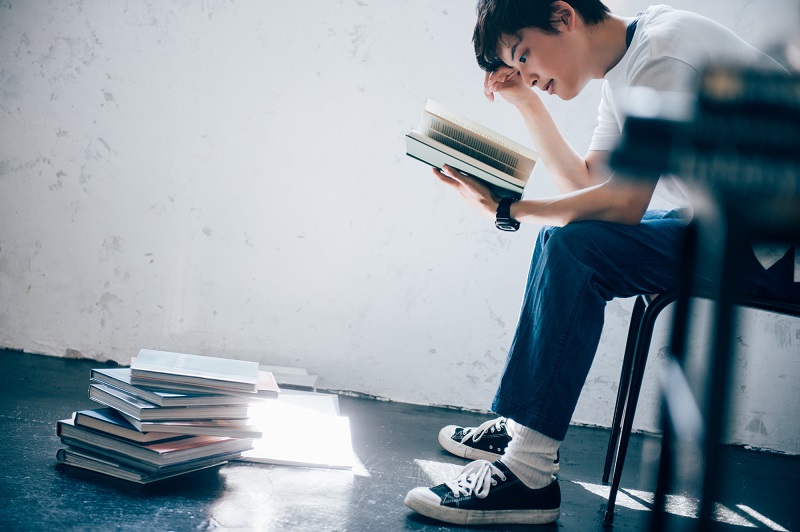
Webテストには法則やコツが存在するため、問題を解けば解くほど簡単にこなせるようになっていきます。
実際に玉手箱の例題を解いてみましょう。
問題集などを使って数多く解くことで、高得点の獲得を目指しましょう。
【対策】計数問題の例題
【例題】
以下の▲に入る数値として、正しい数字を選択肢から選びなさい。
58÷4=▲×2.9
<選択肢>
1.9
2.7.8
3.3
4.5
5.2.2
【回答】
4
【対策】言語問題の例題
【問題】
以下の文章を読み、各設問が選択肢のいずれに当てはまるかを答えなさい。
企業にとって新卒採用とは非常に重要なものである。新卒社員は、新しい価値観を企業にもたらすだけでなく、社員に刺激を与える存在となることが多い。
ある企業では、毎年4月になると、先輩社員へ必死に食らいつこうとする新卒社員を目にすると、自分も頑張らねばならないと自己を奮い立たせたり、手を差し伸べたりするなど、何かしらの変化をする社員が多い。このような社員が増えると、新卒社員の成長速度も早まることになる。
このような相乗効果は、企業が組織として向上していくために非常に重要なことである。
<設問>
1.新卒採用をすることのメリットは、企業に新しい価値観をもたらすということのみだ
2.毎年50%以上の社員が、新入社員によって刺激を受けている。
3.先輩社員が新卒社員に手を差し伸べることは、企業にとって重要なことである。
<選択肢>
- 本文から考えて、設問文は正しい内容だ
- 本文から考えて、設問文は間違った内容だ
- 本文を読んだだけでは、設問文が正しいか間違っているかどうかは判断できない
【回答】
1.2
2.3
3.1
【対策】英語問題の例題
【問題】
選択肢のうち、以下の単語と反対の意味を持つものを選びなさい。
「reject」
<選択肢>
1.pass
2.crash
3.interrupt
4.compare
【回答】
1
まとめ:Webテスト「玉手箱」対策をして就活を有利に!

Webテストには法則やコツが存在しているため、対策をすればするほど合格に近づくことができます。
玉手箱はパターンが想定しやすく、比較的対策をしやすいWebテストになっています。
問題集などを使い事前準備をしっかりして、高得点を狙っていきましょう。
よくある質問
Q. Webテスト「玉手箱」とは何ですか?
Q. 玉手箱とSPIの違いは何ですか?
Q. 玉手箱の出題科目は何ですか?
Q. 玉手箱の特徴は何ですか?
Q. 計数問題の出題形式はどのようなものですか?
Q. 言語問題の出題形式はどのようなものですか?
Q. 英語問題の出題形式はどのようなものですか?
Q. 玉手箱は何割取れれば合格ですか?
Q. 玉手箱の英語レベルはどのくらいですか?
Q. 玉手箱が多い業界はどこですか?
Q. 玉手箱の対策は何日くらいかかりますか?
Q. 玉手箱は1問何秒で解かなければなりませんか?
Q. 玉手箱とCABの違いは何ですか?
Q. 玉手箱の誤答率はどれくらいですか?


監修者
熊谷 直紀
監修者熊谷 直紀
横浜国立大学理工学部卒。株式会社DYMに新卒一期生として2011年に入社し、WEBプロモーションなどのデジタルマーケティング領域で業務に従事し、その後新規事業立ち上げを経験。
2015年よりDYMの人事部へ異動し人事領域を統括、毎年多くの就活生や求職者との面接・面談を実施。
内定チャンネルなどの採用関連メディアへの出演や記事監修を通して人事・人材関連の情報を発信中。

🚀あなたの働き方タイプを診断!
— MeetsCompany【25卒26卒】 (@Meets_Company) January 29, 2025
「私ってどんな働き方が合うんだろう?」その答えがわかる診断を無料公開中🎯
あなたはリーダー?それとも挑戦者?
結果をシェアしてみんなで盛り上がろう!
▼診断はこちら▼https://t.co/zmNLjRt2hM#CATFLIPS #26卒 #27卒 #就活 #診断



